音楽のカテゴライズに逆らって(3) [ミュージック]
3回連続シリーズ
「音楽のカテゴライズに逆らって(1)」
「音楽のカテゴライズに逆らって(2)」
今回はその最終回です

『へるめす』 第37号 岩波書店 1992年5月8日発行より
日本は不思議か
武満 ところで、いまぼくは飛騨という地方から帰って来たばかりなんです。面白いかどうかわからないけど、ちょっとデヴィッドに日本の話をするとね、ぼくが書いている小説『骨月』の5章目ぐらいに出てくる人物がいるんですが、その人物は飛騨の出自なんです。天智・天武の時代に存在したと言われる不思議な泥棒なんです。いわば伝説の主人公なんですが、それは双頭で足が4本あって、手も4本。いわゆるシャム双生児です。ところが、それが大男で、ものすごく速く走る。それは悪人で大泥棒なんだけれど、しかも時の天皇に対して反逆する。その出身地に行ってたんです。
シルヴィアン 何年ぐらい昔の話ですか。
武満 天智・天武だから、千数百年も前でしょうね。
シルヴィアン だけど、一人は必ず後ろ向きに走っているわけですよね(笑)。
武満 そこがぼくはすごくおもしろいと思ったの。一人は前を向いている、もう一人は後ろを向いている。
さて、その飛騨古川にはすばらしい太鼓の伝統があるんです。あんな太鼓はあそこにしかない。ほかには見当たらないんだけど、大きな櫓太鼓に、二人の裸の男が背中合わせに跨るの、馬に乗るようにね。それでこういうふうにバチを――そのバチはその年に出た若い柳の枝でね、両手でそれをはさんで垂直に頭上に振り上げて、打ちおろす。普通太鼓って脇や正面からこう叩くでしょう。そうじゃなくて、太鼓に背中合わせに二人の奏者が晒しの布で互いのからだをくくって、打ち合うんです。とてもすばらしい太鼓でね。
シルヴィアン それは、その伝説と関係があるんですか。
武満 ぼくは関係があると思っています。ところが、きのうも土地の人と話したら、それは関係ないというんです。たぶんその盗賊、両面宿儺というのですが、かれは朝廷に逆らったから、もしかしたら、それで関係がないというのかもしれない。ただ、新しいはその年の柳の枝で叩くというのは、古代の中国では、琴なんかも柳の枝で打って弾かれていたそうだから、それとも何か関わりがあるかもしれないが、それにしても典雅なものです。
シルヴィアン こういった探偵みたいなことはよくなさるのですか(笑)。それから、どうしてそんなことをなさるのですか。
武満 ぼくは朝のうちしか仕事しないもんだから、結構余分な時間があって、いろいろ興味あることのために午後の時間をすごすんです。他に特別理由はありません。
ほんとうはいまでも雅楽なんかで琴が柳の枝で演奏されたりしたら、優雅でいいと思うんだけど、一般の琴は右手に爪をつけて、左で糸を押したりゆるめたりして演奏する。ところが、ある時期から宮中に伝わっている雅楽の琴は左手を一切使わなくなった。それはおかしい、使わないはずはないと思うけれど、もちろん時にはさわるけど音をベンド(曲げる)することは全くタブーなんです。日本の伝統音楽のなかには、いろいろなおかしい、神話的な起源をもった、タブーがいっぱいある。そういうことにとても興味をもっています。真面目な音楽学者というのはあまりそういうことを研究しないんですね。
もうひとつ雅楽の例だけど、笙というマウスオルガンみたいな、バンブーでできた楽器があるんです。一般の吹奏楽器と同じようにいくつもの穴があいて、それを押さえると音が変わる。それなのに、絶対にこれは使わないとう穴があるんです。穴があいていながら、絶対にそれは使われないんですね。どうしてそんなタブーがあるのか、だれに聞いてもわからない。使えば何ということはないし、しかも便利なのに、使っちゃいけないんです。もちろんそうなった原因があるわけで、ぼくはそういうことに興味がある、なぜなのか知りたい。
音楽だけじゃないんですけれど、日本の文化はその殆どが朝鮮半島や中国、また南方からやってきて、オリジンはおよそわかっている。それが日本にきて、たとえば琴なんかの使い方にしてもずいんぶんと変わってきているし、笙などもぜんぜん変わって、たいへん日本化している。その日本化ということにぼくは興味をもってしまうんです。ぼくは外国に行って、よく、どうして日本の楽器を使わないのかといわれる。でも、ぼく自身はそんなことよりも、中国からきたものがどうして日本的になったのかということに興味があるし、もっとその神話的起源を探りたいと思うんです。
シルヴィアン 日本の文化というと、外国にない日本の文化の起源ではなくて、外来の文化が日本にきてからなぜ様式化して、日本人のひとつの審美的な価値観で決まっていったのかということには興味があります。非常に審美的な要素が強いし、はっきりしていますね。それが何世紀も維持されている。それが仏教の影響なのか、神道の影響なのか、神話的なものなのか、私も昔から興味をもっていました。
なにか日本人が理想主義というか、審美的な基準をもっていて、入ってきたものにそれを適用しているのではないかという気がするのですが。
武満 その辺りに関してはぼくは何とも言えない。もちろんそういうことについていろいろ言及している学者はずいぶんいるでしょう。でも、ぼくは不思議なことに、地球上に起こっているいろいろなことを見て、それを背負って、それからそれを相対化していかないかぎりは何もわかってこないと思う。たとえばタルコフスキーがどうしてあんなに水にこだわるのだろうかとか、がどうしてあんなに火にこだわるのだろうか。日本人は同じように、とても水にこだわり火にもこだわっているけど、それはどこの人でもそうで、ことにプリミティブな時代にはみんな火や水に対しては、いまよりももっといろいろなものをそこから読み取っていたにちがいないけれど、それがいろいろな国の伝統文化によって、ある限られた特別な意味をもつようになる。
シルヴィアン たしかに水とか火とか、そういった元素は、どの文化にとっても、とくに原始文化にとっては大事なもので、火とか水はそれぞれの民族にとって同じ意味をもってもしようがないし、民族特有の意味をもつということもありますね。私はもっと日本にこだわりたいのですが、ほかの文化に見られないような、まさにこだわりですね、そういうものを日本に見るんです。それも日本にしか見られない変なこだわりがあるんです。
武満 たしかにそうですね。
シルヴィアン そのこだわりが武士道の文化であったり、男性的な文化であるというのはわかりますけれども、女性的な要素も強いと思うんですけれども……。
武満 よく勉強しているんだなあ(笑)。ほんとにそうです。そういう意味では、非常に大きいテーマだと思います。日本文化はどちらかといえば、女性的要素が強いかもしれませんね。そのことについては、不勉強でちゃんと応えられないなあ。
一緒に仕事をしたい
武満 この前にも話したかと思うけれど、まだ発表したことがないんだけど、以前からテープのための変なものをずいぶんつくっているんです。あなたとミルズのインスタレーションを見ると、あんまり似ているんで、実はぼくはとてもびっくりしているんです。ぼくのそのテープについては、この前もデヴィッドに話したんだけど、聴かせる聴かせると言いながら未だ送ってもいなかった。躊躇していた。60歳にもなった老人が、まだ青年をちょっと過ぎたばかりの人と一緒に何か新しい試みをやろうというのも、あまり健康なことではないんじゃないかという気もしていたから。でも今回、ぼくらのフィールドは同じところにあると思って、ぜひ将来何か一緒に共同で創ってみたいと思いました。
シルヴィアン ぼくも、できたらぜひ一緒に仕事をしたいと思います。
武満 ぼくは自分を変な作曲家だと思っています。たとえばジャズの、ノルウェーのサキソフォン吹きですが、ヤン・ガルバレクなんか、昔からとても面白いと思い、自分に近しいと思っていたら、あまり若いんでびっくりした。デヴィッドもヤン・ガルバレクに昔から興味があることを最近知って、そのことにも驚きと喜びを感じています。だから、別に情報科学の時代だから、地球が狭くなったとは決して思わないけれど、たまたまこの惑星の上に生きていて、同じようなことを感じる人間が存在しているというのはおもしろいことだと思います。
シルヴィアン 情報科学といいますと、メディアはあまりに過剰でオーバーロードしていて、たしかにそれによって世界は小さくなっているのですが、しかしできるだけメディアの余剰なもの、過剰なものから離れて、ある本質とか、ある焦点を追求している人たちがいると思うんです。そういう人たちは、年齢を問わずお互いに惹きつけ合うものがあるのではないでしょうか。
ぼくは最近、ヤン・ガルバレクに会って、それで何か一緒にしたいということを話したんです。そういう意味では世界がだんだん小さくなってきて、いま武満さんとの協力のお話が進んでいるように、彼とも何か一緒にできるというのが自然な成り行きだというふうに考えています。親和性というか、惹きつけあうものがお互いにあるのではないでしょうか。
武満 それは当然の成り行きだろうと思うし、同時にとても喜ばしいことだと思う。というのは、たしかに国際化と言うか、実際地球は狭くなってきているわけで、一つの惑星としてのグローバルな立場で人間は物事を考えなければならないところまで来ているけれど、実際には、いま私たちが、これからいちばん恐れなければならないのはナショナリズムです。それは目に見えない形で、悪魔的な形にだんだん姿をあらわしてくるだろう。そのときに、ぼくらがそれをなんとか食い止めるのは、決して音楽というメディアだけではないけれど、たとえば音楽というメディアを通じてでも、何かお互いに親しく話し合う場を、それからその場の土壌をほんとにいろいろな人間の知恵で豊かにしていくことからだと思うんです。それにはもちろんいろいろな試行錯誤を繰り返すかもしれない。でも、ナショナリズムがもたらす化け物よりは、もっとユーモアのある楽しい試行錯誤だろうと思いますね。
シルヴィアン ぼくもそう思います。だからこそ、ぼくたちは内面的な自己、内面的な存在ということをもっと考えなけらばならないと思うんです。もしそれをしなければ、私たちはもっとナショナリズムとか、愛国主義とか、そういった方向に行くと思います。こういうナショナリズムというものは、人間が不安だから、何かアイデンティティを求めてでてくるものだと思うんです。そして自分が何であるかということを定義するために、表面的な荷物のようなものとしてそれを持ちたがるんですね。しかし、自分の内面に安心と愛と責任というものを感じれば、そういった荷物は必要がないはずだと思います。その責任というものも誰かから与えられたものではなくて、みずからもつ責任、政治制度や国に対する責任ではなく、人類に対する責任、人類に対する愛とでもいうか、芸術というのは愛の延長にすぎないと思うし、芸術は愛の一つの行為だと考えていますので、そういうことを追求している人たちは自然に集まってきて、そして協力をすることができると考えています。
武満 すばらしい。デヴィッドとこんなに有意義な話ができて、ほんとうに嬉しく思います。ぼくの場合はデヴィッドと違って実際に自分が演奏するわけではないし、古典的な意味での作曲という行為が、どれほどこれから今のような形で残るかわからないけれども、それにいままでは作曲者は、ある意味で強者であったけれども、今日、話していると、作曲家というのは強者でなくて、とても弱い、ことばをかえればモデスティな立場に立っている。たとえば、ぼくがデヴィッドの助けをかりて、自分の足が一歩前に進めれば、またそれから先へ歩いていけるような気がする。
シルヴィアン 弱さこそ作曲家の強さだと思います。
武満 久しぶりに充実した会話ができてよかった。ありがとう。もちろんこれが最初で、これからもいろいろな話をしていきましょう。一部のひとたちからは甘いと言われそうですが、実際に、親しい会話や友情、先ずそういうことからはじめなければいまの地球を生き延びさせることはできないと思う。政治だけに頼っていては……。たぶん、政治家は、ああ、あなたたちは非現実的でリアリティがない、と言うんだ(笑)。
シルヴィアン 武満さんの今おっしゃったこと全部、ぼくも感じています。それで、慈悲というか慈愛というものこそほんとの知性の現われだということばがありますが、政治家にはそういったものが感じ取れませんね。
武満 今度の坂本龍一のコンサートでは、デヴィッドはどういうことをやるんですか?
シルヴィアン 2曲です。ニューヨークでレコーディングした曲が一つと、『戦場のメリークリスマス』のサントラからとったもの、その二つをやります。
武満 次のプランは何ですか?
シルヴィアン ロバート・フリップとのジョイント・コンサート。3月に日本で。
去年1年間、武満さんは60歳を迎えていろいろなイベントがあったのですが、何か氷のなかに入って冷凍保存されたような、そんな気分になってしまうんじゃないですか(笑)。
武満 ぼく自身は特に何も感じていない。まだ、しなきゃならないことがあるし。
シルヴィアン 武満さんがそれの影響を受けるとはまったく思っていませんけれども、ただ、60歳ということを騒がれるというのは、たとえば日本人だからというふうに外国で騒がれるような、そういうひとつのステレオタイプですね。そういうふうに、この人は日本人だからこうあるべきだということを強要されるように、この人はいま60だからこうあるのだと強要されるイメージがあるから、それに対して戦わなければいけないと思います(笑)。
武満 ありがとう。それはほんとうにそうだ。
あなたたちはそんなことはないと思うんだけど、ぼくのような音楽だと、外国に出た時によく日本人であることを強制されるんですね。それがときどき耐えられなくなる。みんな期待しているわけ。ぼくから非常に日本的なものを。でもね、それに慣れたらいやだし、そういう意味ではひとの期待を裏切りたい。それこそ大いなる愛の裏切りです(笑)。
でも、何か一緒にやりましょう。ヴァージン・レコードはいやだというかもしれないけれどね。60歳のヴァージンじゃね(笑)。
1992.2.4 in Tokyo
David Sylvian・ミュジシャン
たけみつとおる・作曲家
今日の1曲
世界のTekemitsu から絶賛されちゃったからには、外すわけにはいきません
Epiphany 「エピファニー」/ David Sylvian& Russel Mills
https://www.youtube.com/watch?v=NmGUa5DL0Xg

Ember Glance: Performance of Memory
今では輸入盤さえ入手は難しいようです
なお、『へるめす』の編集同人が昨年また一人、お亡くなりになってしまいました
中村雄二郎さん死去
哲学者「共通感覚論」「術語集」

著書「共通感覚論」「術語集」など幅広い分野での独自の論考で知られる哲学者で、明治大名誉教授の中村雄二郎さんが、老衰で26日に死去したと、所属していた明治大が発表した。91歳だった。葬儀は近親者で営んだ。後日しのぶ会を開く予定。
東京生まれ。東大文学部を卒業し、文化放送を経て明大教授などを歴任した。パスカルやデカルトを中心としたフランス哲学を出発点とし、60年代には人間の生の根源である情念に注目した論考を発表。70年代以降は、人間の認識のあり方を根源的に考え直す共通感覚論やトポス(場所)論などを展開した。
生きた学問としての哲学を重視し、科学技術や生命倫理、21世紀の戦争やテロなどのテーマに積極的に発言した。おもな著作に、「魔女ランダ考」「西田哲学の脱構築」「悪の哲学ノート」など。入門書を数多く手がけ、84年に刊行された「術語集」は、哲学書としては異例のベストセラーとなった。
(昨年8/31付朝日新聞より)
謹んでご冥福をお祈り申しあげます


哲学の現在―生きること考えること― 岩波新書
術語集―気になることば― 岩波新書
 >
> 

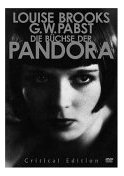
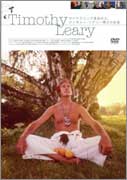













コメント 0